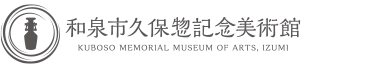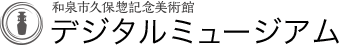トップページ > デジタルミュージアム > 検索結果
青銅 方相氏双龍文帯鉤

| 作品名 | 青銅 方相氏双龍文帯鉤 (せいどう ほうそうしそうりゅうもんたいこう ) |
|---|---|
| 時代 | 明〜清 |
| 地域 国 | 中国 |
|---|---|
| 分野 | 美術 |
| 員数 | 一点 |
| サイズ | 長15.4cm |
解 説
帯鉤は帯留め(ベルトバックル)として使用されたもので、戦国時代から漢時代にかけて数多く製作されている。先端の鉤首(フック状の部分)と鉤面(文様が表される本体部分)の裏面にある鈕(茸形をした突起)を、帯(ベルト)の両端に設けた孔に引っ掛けて装着した。
熊の皮をかぶった四つ目の神・方相氏は、右手に戈、左手に盾をとり、疫病をしりぞけ、葬送の路を開く神であった。南北朝時代から墓室の壁面などにも描かれている。そのような神がなぜ帯鉤の意匠にされたか、いくつか同じ文様の帯鉤が知られている。葬送の衣装に添えられた帯鉤だろうか。
地金は赤みをおび、緑錆は単調で変化に乏しい。方相氏を表した帯鉤は、ある程度の大きさがありながら、意匠は縦方向になり、しかもなにものかをかけるとなれば図像の天地が逆になる。近世になって工夫された特殊な用途に供されたのであろう。鈕に蛙が表され、裏面には「宜□富□」という4字の刻銘がある。(江川淑夫氏寄贈品)